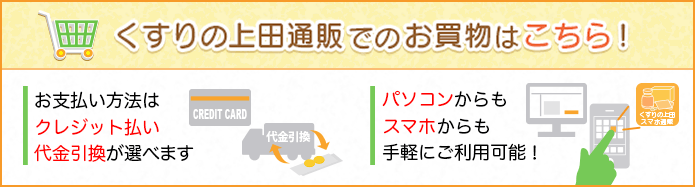【2022年】不妊治療の「保険適応前」と「適応後」で何が変わった?

2022年4月より、不妊治療が保険適応に変わりました。
保険が使えるようになって、便利になった部分もあれば、人によっては治療費の負担が増えた場合もあります。
不妊治療が、保険適応前と適応後では、どのように変わったのか、解説していきますね。
このページの目次
・不妊治療の支払い金額
【保険適応でこう変わった】
・治療内容にも変化が
【保険適応と保険外診療】
記事担当:薬剤師(上田康晴)
不妊治療の支払い金額【保険適応でこう変わった】

影響が大きく感じる部分を先にお話しします。
それは、皆様がお住まいの「都道府県・市町村」から、不妊治療に対して「不妊治療助成金」として補助金がもらえてた部分が、廃止された事です。
【保険適応前は】
まず自由診療であった人工授精・体外受精は、病院の治療費を自己負担で全額支払い、後から補助金がもらえるシステムでした。
【保険適応後】
3割負担で治療費を支払い、不妊治療助成金はもらえなくなった。
※一部の市町村では個別でもらえる場合あり。
ただし体外受精で高額になる場合は、「高額医療制度」を使うことで3割負担ではなく、限度額以上の支払いは発生しない。
不妊治療助成金は、都道府県によってルールや補助金の金額が違っていました。
【保険適応後で治療費が逆に高くなった人】
全員に当てはまる話ではありませんが、不妊治療の保険適応前では、高額の体外受精をしても実質タダの場合も結構ありました。
実際の治療費分が、ほぼ全額「不妊治療助成金」で戻ってくるパターンです。
そうした実質無料だった方は、保険適応で3割負担になったので、治療費は増えたことになりました。
【保険適応により治療費が安くなった人】
住まいの県によっては、夫婦の所得制限があった場合もあり、そうした方は「不妊治療助成金」がもらえなかった場合や、県や市町村の補助金が少なかった場方もいます。
そうした方は、体外受精などが保険診療になって3割負担となり安くなるケーズもありました。
つまり、保険適応で安くなった方もいれば、高くなってしまった方もいる現状でした。
ただ残念だったのは、体外受精の保険診療の「年齢制限」の撤廃があれば助かった方は、多かったのですが、これは叶わぬ夢となってしまいました。
体外受精は43歳以上は保険適応外。
⇒厚生労働省のHP(保険適応リーフレット)
関連記事はコチラ
・体外受精、人工授精【保険適応の費用,回数,年齢制限など】
・人工授精の金額は?【保険適応の費用】
・【不妊治療】【体外受精】の「始め方」や「転院」の仕方
不妊相談はお気軽に
少し難しい話が続きましたが、お店でのお客様との「不妊カウンセリング」では、もっと簡単でわかりやすい妊活アドバイスをしています。
不妊でお悩みの方は、不妊相談の実績、経験豊富な当店「くすりの上田」まで、お気軽にご相談くださいませ。
相談無料ですが、相談に時間がかかるため事前予約をお願いしています。
不妊相談ができる薬屋
(ネット通販もやっています)
くすりの上田
富山県高岡市大手町11-30
(高岡大仏の真横)