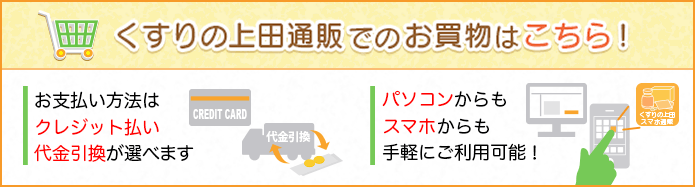不妊の原因:年齢の壁は大きい【いつまで妊娠できる?】妊娠の確率
(記事更新日:2020/08/11)
こんにちは、薬剤師の上田康晴です。
年齢とともに、妊娠のハードルが上がっていきます。
今回はその原因について、お話します。
不妊と年齢の関係

不妊の一番の原因が、年齢と言っても過言ではないでしょう。
年齢が20代、30代、40代となるにつれ、妊娠のハードルは上がっていきます。
現在では、晩婚化で結婚する年齢が高くなっています。
それが日本の「不妊」の大きな原因にもなってきています。
年齢が高いと、なぜ妊娠しにくくなる?

どうして年齢が高くなると、妊娠しにくくなるのでしょうか?
それは「卵子」が老化するからです。
女性の卵子は、赤ちゃんの時からある細胞を保存していて、それを毎月「排卵」しています。
20歳の方は、20年間、卵巣の中で年数の経過した卵子(原子卵胞)が排卵しようとします。
35歳になれば、35年間の年数の経った卵子が排卵されます。
血液などは、定期的に新しいものを作っています。
常に新しく入れ替わっています。
ですが「卵子」は生まれた時がいちばん新しく、どんどん老化・劣化していきます。
30代、40代になってくると、卵子の「劣化」や「染色体異常」が増え、それが妊娠の妨げにもなっているのです。
流産率は年齢が上がると高くなる
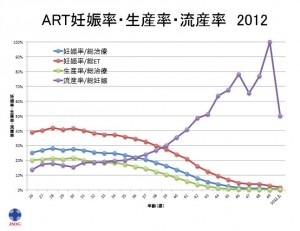
横軸が年齢、縦軸が確率率のグラフになっています。
やはり、年齢が上がってくると、妊娠率は低下しています。
また、1本の線グラフだけ、右肩上がりになっていると思います。
この紫色の線が「流産率」です。
40代にもなると、卵子の染色体異常が増えてくるため流産も多くなっていきます。
できるだけ、早く妊活することはとっても大事な事なのです。
年齢が高い人への妊娠アドバイス

■妊活を始めたばかりの方(~6か月)
まずはしばらく「タイミング」のチャレンジでもOKです。
■半年以上になる方
不妊の基礎検査くらいは、しておいたほうが安心です。
不妊の基礎検査
・ホルモン検査(血液検査)
・排卵のチェック
・卵管が通っているかの検査
・精子の検査
■1年以上になる方
ステップアップの不妊治療を検討しましょう。
・人工授精
・体外受精
年齢や、ご夫婦の体調によって、治療プランのスケジュールは変わってきますので、詳しくは病院やクリニックの先生と、しっかり話し合うといいです。
くすりの上田にも、お気軽にご相談くださいませ。
「補腎の漢方」が年齢の対策にお勧めです

年齢による不妊リスクは、卵子の老化以外にも、漢方的に考えるならば
・体を作る力
・機能を維持する力
こうした働きが低下してくため、妊娠力が落ちてくるとも考えられます。
若返りは無理でも、漢方薬を上手に使う事で、低下した体の機能を高めることは可能になります。
当店では35歳以上の不妊相談の方には、できるだけ漢方でいう「補腎」対策を心掛けております。
臓器の「腎臓」の「腎」という文字を書きますが、内臓としての腎臓とは、分けて漢方では考えます。
腎の「陽」のエネルギーが低下してくると
・冷えやすかったり
・寒がりであったり
・元気が出なかったりします。
漢方では、このような症状を「腎陽虚」といいます。
腎の「陰」のエネルギーが低下してくると
・生理不順になったり、
・イライラしたり
・ほてり、のぼせ
・目や口、肌の乾燥
・月経量の減少
などがあらわれます。
漢方では、このような症状を「腎陰虚」と言います。
こうした、バランスの弱りが「妊娠しにくい体」へとなっていくのです。
腎のエネルギーは年齢でどう変わる?

腎のエネルギーは、漢方の考えだと、生まれてから次第に高まっていき、30歳頃にはピークを迎え、あとは年齢と共に低下していくと言われます。
ですので本来なら人間は「30歳頃」までに、妊娠、出産を終わらせておくのが、ベストな状態と思われます。
ですが日本では近年、晩婚化の傾向があり、いざ「赤ちゃん」が欲しいと思い始めるのが、30代からというケースが増えてきています。
年齢による不妊の原因は
1つは卵子の老化。
2つ目として、漢方的にみると、
腎の弱りが考えられます。
補腎の漢方はこんな方に
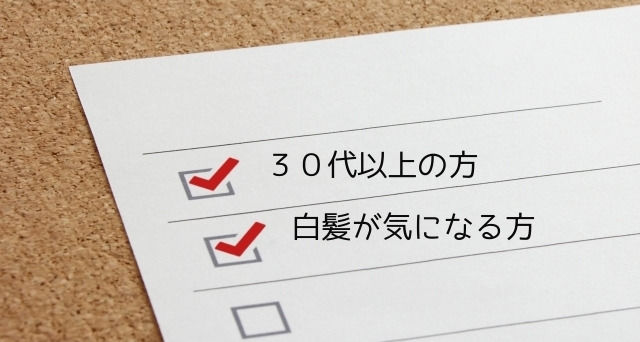
子宝対策で、いろいろ飲んでいるけど
今ひとつ・・・という方は
是非、一緒に「補腎の漢方薬」を飲んでみてください。
腎の弱りのサインとして
・疲れやすい
・白髪が出てきた
・夜間にトイレに起きる
・手足が冷える
・排卵が弱い、卵子の質が悪い
・耳鳴りがする
・むくみがある
・目が疲れる
・精力減退
・肌が乾燥する
・のぼせ、ほてり
・生理の出血量が減ってきた
などがあります。
補腎の漢方薬の紹介などは、お気軽に「くすりの上田」まで。
記事担当
薬剤師:上田康晴
不妊相談の薬屋さん
くすりの上田
関連記事
流産の原因や確率は?【健康な出産のための情報まとめ6選】
子宮内膜の厚さの基準値【内膜の厚さアドバイス3選】